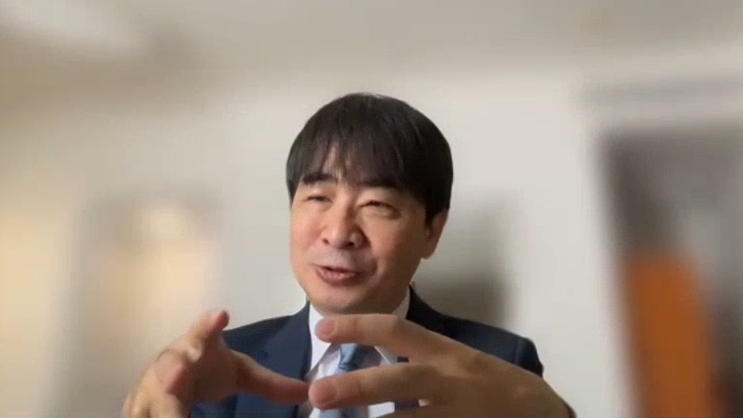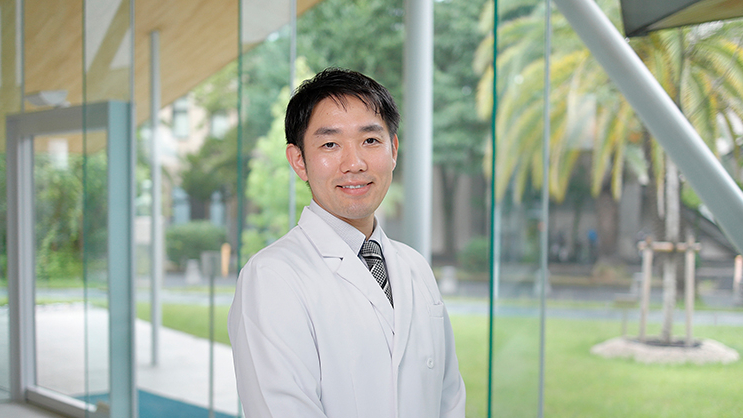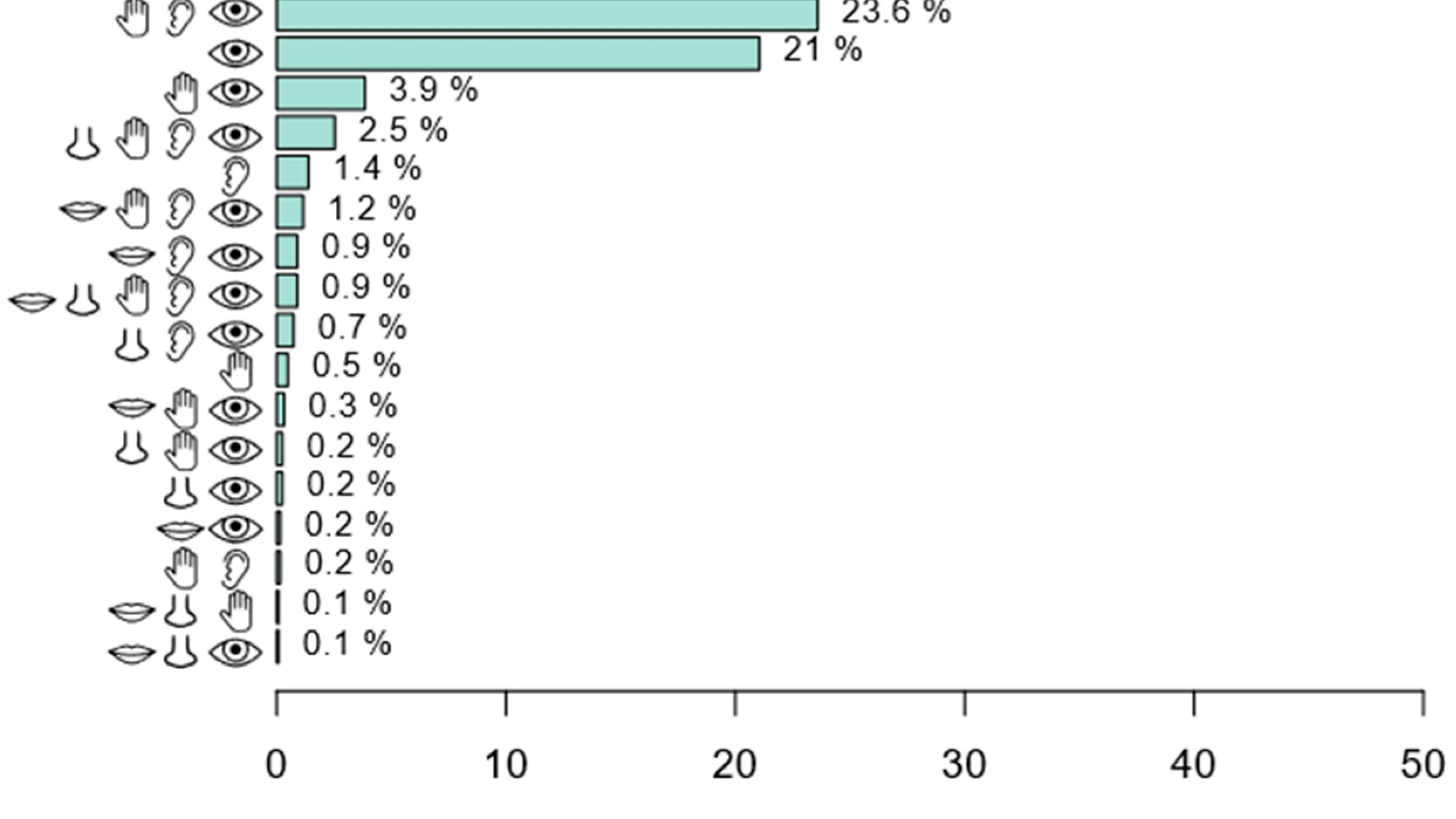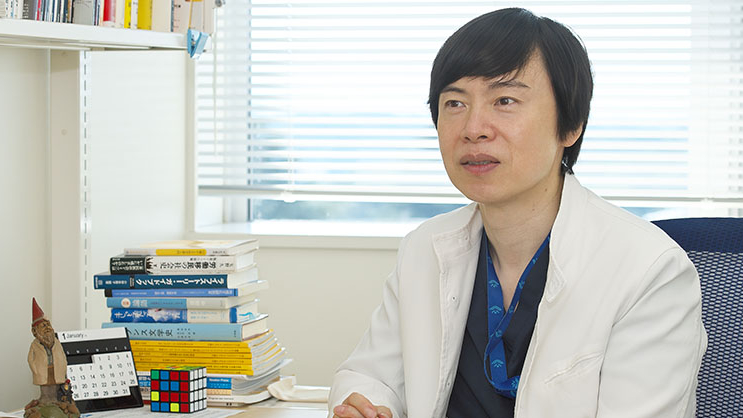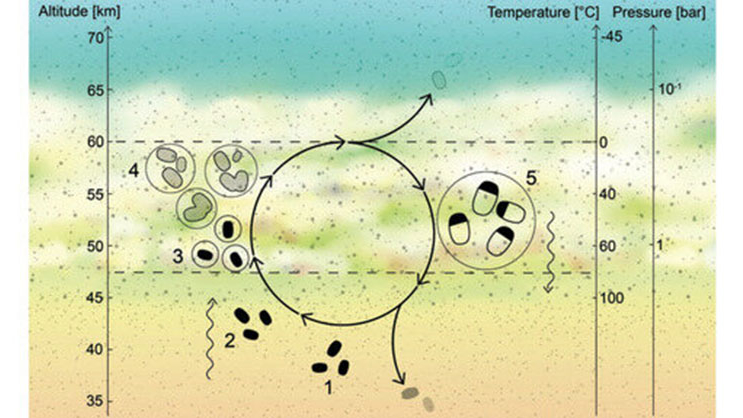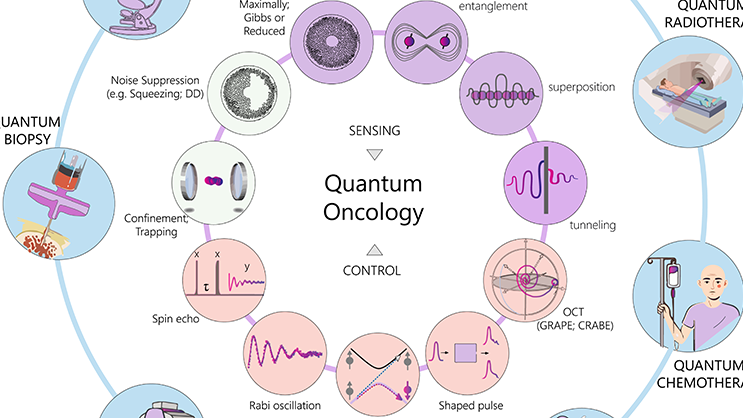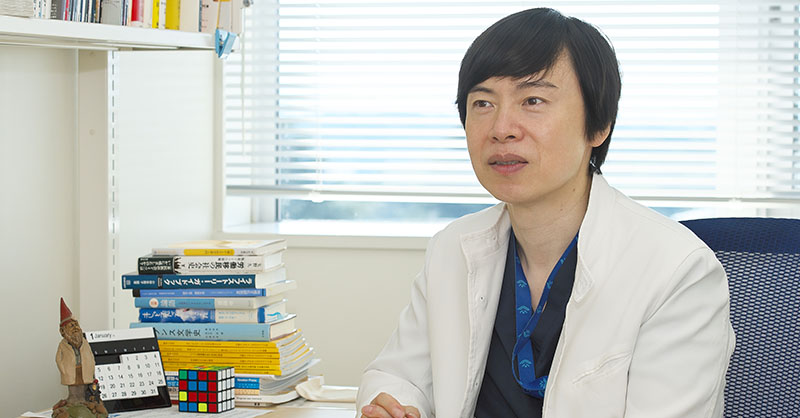
デジタル時代の新しい生活習慣病・ゲーム依存がもたらす社会的リスク─今高城治先生インタビュー【後編】
本記事は後編です。前編はこちら
──2024年にDeseasesに投稿いただいたレビュー論文『Youth Suicide in Japan: Exploring the Role of Subcultures, Internet Addiction, and Societal Pressures』 では、ゲームだけでなく、広く日本の独特なサブカルチャーが若年層のメンタルヘルスに与える影響について言及されています。この論文のポイントについても教えてください。
日本は世界的に見ても若年者の自殺が非常に多い国です。特にこの2年間は過去最高を記録し、これまでは10代後半が多かったのですが、プレティーン世代の11~12歳くらいも増えてきました。少子化対策としても、これは国を挙げて取り組まなければならない重要な問題であると考えました。
この背景として、ゲームも含め日本特有のサブカルチャーが関連している可能性について議論しているのがこの論文です。
日本には昔から死を美化する文化があります。文学では太宰治や三島由紀夫が若者に支持され、少年向けの漫画でもごく一般的に殺し合うシーンなどがあります。J-POPの歌詞もそうです。また、人気の芸能人が亡くなるとワイドショーなどで大きく報道され、それに影響されてしまう人も多いです。こうしたメディア・コンテンツの暴露から若年層を守るための政策の必要性について、論文で啓発しています。
──ゲームやアニメ、漫画などのサブカルチャーは、それが共通の話題になって友達が増えたり、好奇心を満たしてくれたり、子供時代を豊かにしてくれる可能性も持つと思います。こうしたメリットとデメリットのバランスについてはどう考えますか?
私自身も、その存在自体が悪いとは思っていません。包丁を売っていることが殺人と結び付けられるわけではないのと同じことです。ただ、低年齢層にそういったものが容易に暴露されることのリスクについては、子どもの心を育む社会環境として慎重に考えていかなければならないと思います。
ゲーミフィケーションやe-スポーツなど、ゲームには良い側面もたくさんあります。2013年には、スーパーマリオのプレイによって脳の灰白質が増加したというデータが報告され話題になりました。
研究職として、バイアスを排除することは非常に重要なことだと考えています。例えば「ゲームが悪い」と思って研究計画を立てると悪いデータが出やすくなりますし、逆に「ゲームが良い」という仮定をたてるとゲームが良いというデータが出やすくなります。客観的な視点から事実を積み重ね、社会全体の利益につながる道を模索していくことが必要だと思います。
──ゲームが子どもに与えるリスクとどのように向き合っていけばよいのでしょうか?
家庭や個人の責任にとどまらず、社会全体で枠組みを整えるべき段階に来ていると考えます。日本では、国策としてゲーム、アニメ、漫画、デジタルコンテンツを積極的に輸出し、企業を支援してきた構造があり、なかなか規制をたてることが難しい土壌があります。歴史的にも日本は世代を超えてゲームを楽しむ文化を持ち、ゲーム依存は個人の問題として処理されがちです。
過去にはパチンコや酒、タバコなどに対して未成年を守る条例や法律が整備されてきました。しかし、ゲームには同様の規制が存在せず、幼児でも無制限にアクセスが可能です。国が政策を通じてインターネットゲーム障害の早期予防に取り組む必要があると思います。
──日本以外の国ではどのように対策されているのでしょうか?
中国では未成年は夜22時から朝8時まではゲームにログインできず、課金額の上限も設定されています。プレイの際は個人番号の入力が必須で、1日のプレイ時間を超えると自動的にシャットダウンされる仕組みがあります。韓国では「シンデレラ法」により、深夜0時にはオンラインゲームが国によって一斉に停止され、かつて深刻だった依存問題が改善されました。
スマートフォンは「デジタルドラッグ」としての性格を持ちます。スティーブ・ジョブズも自分の子どもにスマートフォンの使用制限を設けていたという逸話もあるくらいです。ゲーム依存が脳の発達期に深刻な影響を与える可能性を考えれば、日本もなんらかの対策を打つべきでしょう。
──今後、先生はどのような活動をしていきたいと考えていますか?
医療から教育現場へ、そして福祉や行政へと順番に進めていきたいです。3歳児健診や5歳児健診の場でも、ゲームのリスクについてきちんと啓蒙していくつもりです。
まずは私のいる栃木県で、県の「子どもの心支援相談員」のような行政ポストに入ったり、委員会を立ち上げたり、様々な場で講演活動をしていきます。ある都道府県がモデル地域になると、そこを起点に広がっていくでしょう。
一方で学術研究も並行して進める必要があります。単に「これは良くない」と声を上げても、学術的な裏付けがなければ誰も取り上げてくれません。地域でのフィールドワークとアカデミックな研究を橋渡ししながら、社会還元していきたいと考えています。
──貴重なお話をありがとうございました。最後に、多数の論文をMDPIにご投稿いただいている立場から、MDPIに対してどのような印象をお持ちかお聞かせください。
私が今取り組んでいるインターネットゲーム障害に関する研究は、アカデミックの一部のコミュニティの中だけで共有され、そのまま眠ってしまうような論文ではないと考えています。北米やEUだけでなく、グローバルな視点から広く社会的なインパクトを生み出したい時、MDPIのジャーナルは非常に良いと思います。すべてのジャーナルがオープンアクセスで拡散力がありますし、論文のWEBページには被引用数などが明確に表示されていて、どのくらいアクセスされているかも分かりやすいです。世界中に広めたい研究成果を出すとき、MDPIは有益な選択肢となっています。
▼本記事の前編はこちら
(聞き手・文:MDPI Japan 鈴木)
今高 城治(いまたか・じょうじ)先生プロフィール
1994年、獨協医科大学医学部を卒業後、慶應義塾大学文学部・法学部、早稲田大学人間科学部eスクールを卒業。現在、獨協医科大学医学部小児科学教授を務める。同大学を拠点に研究・教育・臨床に携わる一方、防衛省特別職国家公務員医官(二等陸佐)、ローマ・バチカン市国バンビーノジェズ客員教授(2016–2017)、英国アングリア・ラスキン大学MBAなど、国際的かつ多方面にわたる活動を展開している。